卒業生・その他
医13期生
尾関 祐二
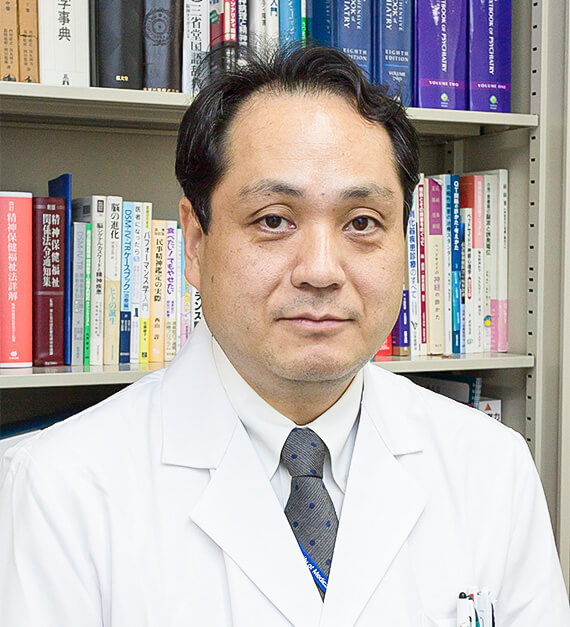
自分にとっての滋賀医科大学体験は困惑のもとに始まった。今振り返ると、滋賀とはどんな地であるのか理解できていなかったこと、そもそも医学部に入学したが、それが実際に何を意味するのかほぼ自覚できていない状態であったことが困惑の理由であったように思われる。そこでまず思い出されるのは井戸庄三先生である。滋賀県以外の出身者に対して滋賀を知ることを強く説かれ、滋賀に関する知識の基盤を頂いた。今となっては当たり前のことではあるが、医療を実践するには地域を知らないといけない。当時そうしたことには無自覚ではあったが滋賀の知識を授けてもらったことは、今の診療にも役立っているし、どの地で働いても地域を意識するという姿勢の形成にも影響を与えてもらった。そして学年が進み諸先生方にいろいろな指導をいただくことで、医師の役割がおぼろげながら見えてきた。ただの労働といった観点では医師という仕事は把握できない。時に傲慢と敵視されるようなことがあっても、何らかの確固たる思い、医療に対する姿勢がないと継続することがむずかしい役割であるように感じた。また、時に先生に対して失礼なこともしてしまったと後悔することもあるが、そうしたダメな経験を含め少しずつ、医師の自覚が芽生えていったように思われる。こうして知識や意識を授かって卒業。本学精神医学講座に受け入れてもらって、医師生活が始まった。ここで初めて気が付いたのが当直の存在であった。夜病院に泊まって、自分で判断して、朝になっても家に帰らない。病棟スタッフに指示を出す立場であることを知って(当たり前)医師の役割を実感する体たらくである(しかも実際にはしっかりした指示など出せなかった)。結局は自覚に乏しい情けない状況からの医師生活の始まりであったが、幸運であったのは滋賀医科大学精神医学講座への入局であった。当時医局で指導していただいていた先生方は、その半数以上がのちに大学精神科の教授になるなど非常に活動的であった。標準的な精神医学、科学的な根拠を伴った診療と研究(今だとEBMなど言うのでしょうか)。当時の精神科医としては決して多くはないような体制での研修から精神医学を開始できた。これは本当に幸運であったとともに、高橋三郎教授には感謝しかない。なお高橋先生には今でも本学の学生講義を担当していただいている。私としては、してもらったことを後輩にどれくらいできるのかが日々の課題となっている。
本学50周年に寄せて、自分語りとなってしまったが、滋賀医科大学の教育によって一人の精神科医が出来上がっていく過程を通して滋賀医科大学の一面を表すことを試みた。



